岸田首相は、8月21日、全漁連の坂本会長と面談した際「なりわいが継続できるよう必要な対策をとり続ける」と約束しました。
政府は、風評対策として水産物の販路拡大や買い取りなどの需要対策に300億円。
漁船の省エネ化の後押しなど漁業継続支援に500億円のあわせて800億円の支援を決めています。
漁業者の懸念を払しょくし、継続できるようにするためには安全性に対する消費者の理解も欠かせませんが気になるデータもあります。
福島中央テレビは、ヤフーニュースと共同で、7月下旬に全国3000人を対象に処理水に関するアンケートを行いました。
そこで「消費者である国民の理解は得られたと思うか」とたずねたところ、約半分が「理解は得られていない」と回答しました。
放出を間近に控える中、処理水に関する科学的な安全性が十分に浸透していないことが伺えます。
一方で、国と東京電力のこれまでの姿勢については意見が分かれています。
「処理水放出に関し、国と東京電力は理解を得るために取り組んでいたと思うか」聞いたところ、漁業者に対しては優位な差は生まれませんでしたが、消費者に対しては「取り組んでいなかった」が「取り組んでいた」を10ポイント上回る結果となりました。
そして、懸念される風評被害についてです。
仮に、風評被害が生じた場合、その原因は何なのかアンケートで伺うと…その結果は「不安をあおる情報やデマが流布されているから、安全安心に関する科学的根拠に基づいた情報が不足しているから」の2つが大きく占めていました。
そこで、原子力工学が専門で廃炉対策チームのメンバー、東京大学大学院の岡本孝司教授に、国と東京電力、そして私たちに求められている事を聞きました。
まずは、放出後に国と東京電力はどういう姿勢であるべきか…です。
■東京大学大学院 岡本孝司教授
「正確性と公開性というオープンな姿勢ですね。すべての事象、データを加工とかをせずに、生データを含めてしっかり出していく」
情報をIAEAや世界中の人が分析できるよう透明性を確保し、信用を積み上げていくというものです。
そして、私たちにも、処理水と向き合っていく上で大切な役割があると指摘します。
■岡本孝司教授
「デマが起きたとしても、起きるとしても、そこは(放出を)やっておくことが、将来の人々、日本人にとって極めて大きな前進になります。福島の事故を起こしたのは東京電力の責任かもしれませんし、国の責任かもしれません。しかしながら、ぜひ日本の将来のために、福島の将来のために1人1人がぜひご協力いただいて、無用な心配をなさらずにですね」
私たちが関心を持ち、その安全性を見守ることも、風評被害の払しょくにつながっていきます。
<記事はこちら>
https://www.fct.co.jp/news/area_news_2809


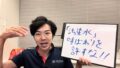
コメント