2025年現在、インボイス制度により多くの国民(特にフリーランスや税務署など)から多くの悲鳴が止まらない状態が続いています。
インボイス制度の悪影響と廃止に向けた道筋について。
2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を厳格化する仕組みとして始まったはずが、導入直後から中小企業事業者やフリーランスを中心に猛反発を呼んでいます。岸田文雄政権(すなわち宮沢一族)で強行されたこの制度は、売上高1,000万円以下の免税事業者を課税事業者に転換せざるを得ない状況を生み出し、実質的な増税と事務負担増大を強いる「悪法」として、多くの国民から非難の的となっています。
特に、副業としてイラストレーター、ライター、声優、配送ドライバーなどを営む人々にとっては、気軽に収入を得る機会を奪う存在です。税務署内部からも、登録者の申告漏れ対応や相談件数の爆発的増加に苦しむ声が漏れ聞こえ、現場の混乱を物語っています。この制度を廃止するためには、国民の声が政治を動かすしかありません。以下では、まず問題点を整理した上で、高市早苗総理率いる高市政権が取るべき行動と、国民(特に副業者)が取り組める具体策を、解説します。
インボイス制度の問題点:なぜ「真っ先に廃止」すべきかインボイス制度の核心は、課税事業者しか発行できない「適格請求書(インボイス)」を保存しなければ、仕入税額控除が受けられないという点にあります。これにより、免税事業者(主に中小・個人事業主)は取引先から「登録せよ」と圧力をかけられ、登録すれば消費税納税義務が発生。登録しなければ取引排除や値下げ要求が横行します。結果として、制度導入から2年経った2025年現在も、以下のような深刻な影響が広がっています。
経済的負担の増大と廃業ラッシュ:免税事業者の約8割が税負担を価格転嫁できず、所得や貯蓄から捻出せざるを得ない状況です。全国商工団体連合会の調査では、登録者の4割以上が「税支払いが家計を圧迫」と回答。農家、建設業の一人親方、芸術家(アニメーター、漫画家など)が廃業に追い込まれ、2024年の廃業件数は前年比15%増(中小企業庁推計)。副業者にとっては、月数万円の副収入が消費税分(約10%)減少し、モチベーションを削ぐ悪循環を生んでいます。
事務負担の爆発:請求書の税率確認・保存義務が経理業務を倍増。中小企業では、システム改修や教育費用で数百万円のコストが発生。国税庁のデータでは、2024年のインボイス関連相談が前年の3倍超に達し、税務署員の離職率も上昇。内部からは「登録者の申告漏れ追及に追われ、本来の業務が回らない」との不満が噴出しています。
社会・文化への悪影響:フリーランスの声優やイラストレーターが「もう生きていけない」と悲鳴を上げ、業界全体の多様性が失われつつあります。STOP!インボイス(インボイス制度を考えるフリーランスの会)の調査では、回答者の半数近くが「取引減少」を報告。地方経済では、個人タクシーやシルバー人材センターの会員が打撃を受け、高齢者の貧困を加速させています。
税務署からの廃止声:税務署員の匿名投稿や内部文書から、「お尋ね文書」の乱発で事業者との信頼関係が崩壊」「相談窓口がパンク状態」との声が相次いでいます。2024年の国税庁内部報告書でも、運用コストが税収増を上回る「逆効果」を指摘。国民の声だけでなく、現場からも廃止論が強まっています。
これらの問題は、制度の「公平性向上」という名目が、弱者切り捨ての増税装置に成り果てた証左です。2025年現在、廃止の可能性は低いものの、地方議会からの反旗(例: 埼玉県議会での自民提出意見書可決)が全国に波及しつつあり、政権交代や世論圧力が鍵となります。高市政権が取るべき行動:廃止実現のための具体策として、高市早苗総理は、過去に消費税減税に慎重ながら「中小企業支援」を強調してきましたが、インボイスについては明確な廃止表明がありません。2025年10月の所信表明演説でも触れず、国民の失望を招いています。高市政権が本気で廃止を目指すなら、以下のステップを即時実行すべきです。これらは、制度の悪影響を最小限に抑えつつ、税収確保の代替策を講じる現実的な道筋です。
即時凍結と検証委員会の設置:導入から2年経過した今、政権発足直後に「インボイス運用凍結」を宣言し、第三者委員会(中小企業代表、税務専門家、フリーランス含む)を設置。半年以内の影響調査を実施し、廃止の科学的根拠を積み重ねる。埼玉県議会の意見書のように、自民党内からも廃止論が高まっているため、党内調整は可能。凍結中は経過措置(80%控除など)を無期限延長し、副業者の負担を軽減。
廃止法案の国会提出と与野党協議:高市政権として、2026年通常国会に「インボイス廃止法案」を自民党主導で提出。野党の廃止法案(立憲民主党の2022年提出分)を参考に、消費税全体の見直し(軽減税率廃止+給付付き税額控除導入)をセットで進める。これにより、インボイスの「複数税率対応」という口実を解消。財源は、法人税の富裕層向け累進強化や無駄な公共事業削減(例: 防衛費の優先順位見直し)で賄う。税務署の負担軽減のため、廃止後の簡易申告システムを整備。
支援策の拡充と代替税制の構築:廃止までの移行期に、登録事業者への一時金支給(1事業者あたり50万円上限)や、無料の経理ソフト提供を義務化。副業者向けには、年収1,000万円以下の「副業免税枠」を新設し、気兼ねない活動を保証。税務署内部の声に応じ、相談窓口を倍増し、廃止後の税務行政をデジタル化(e-Tax完全義務化)で効率化。全体として、消費税依存を減らし、所得税の累進強化で公平性を確保。
国際比較と世論喚起:欧米諸国では類似制度が中小保護措置付きで運用されており、日本の高負担は異常。高市政権は、OECD報告を基に「日本型インボイスの失敗」を国際的に発信し、国内世論を味方につける。総理直轄の「中小活性化タスクフォース」を立ち上げ、地方自治体との連携で廃業防止基金を創設。
これらを実行すれば、高市政権の支持率は中小層で急回復し、「国民目線」のイメージを確立できます。逆に放置すれば、税務署の混乱が政権の足を引っ張るリスク大です。
国民(特に副業者)が取り組める具体的な行動:声を形に変える廃止は政権任せではなく、国民の草の根運動が不可欠です。特に、副業希望者(サラリーマン並行のクリエイターなど)は、制度の「気軽さ喪失」が直撃する立場。以下は、誰でも即実行可能な取り組みです。個人でコツコツ、または団体で連携を。
署名活動の継続と拡大:STOP!インボイスのオンライン署名はすでに59万筆超(2025年時点)。Change.orgなどで新たに「高市政権への廃止要請署名」を開始し、SNSで拡散。副業者向けに「副業インボイス廃止」のハッシュタグを使い、体験談(例: 「月5万円のイラスト収入が税で半減」)を投稿。目標: 100万筆で国会請願。地方議会(市区町村レベル)へも意見書提出を促すテンプレートを共有(埼玉モデルをコピー)。
SNS・メディアでの発信と連帯:X(旧Twitter)で「インボイス廃止」をキーワードにポストし、税務署の内部声(匿名投稿)を引用。副業者コミュニティ(例: フリーランス協会、クリエイターDiscord)で情報交換会をオンライン開催。著名人(声優の岡本麻弥氏ら)の反対発言をリポストし、波及。地元メディア(新聞投書、NHK視聴者投稿)へ「税務署の負担増で行政崩壊寸前」と訴え、世論を喚起。
議員・行政への直接アプローチ:地元選出の国会議員(自民含む)にメール/面談で陳情。「副業で家族を養うのに、登録で年10万円の税負担は耐えられない」と具体例を添付。高市政権の閣僚(片山さつき財務相ら)に公開質問状を送付。税務署へは「廃止陳情書」を複数人で提出(国税庁Q&Aを逆手に取り、運用混乱を指摘)。副業者向け: 登録せず取引を維持するための「免税事業者連合」を作り、大手取引先へ「インボイス不要の価格調整」を交渉。
選挙・デモでのアクション:2025年参院選を廃止のターニングポイントに。廃止公約の野党候補に投票し、自民候補へ公開質問(街頭演説でマイク突っ込み)。全国一斉デモ(10月1日の国会前デモをモデルに、副業テーマの分科会を追加)。オンライン署名をオフラインに繋げ、商店街でチラシ配布。「インボイス廃止で副業ブーム再燃!」とポジティブに訴え、参加者を増やす。
日常レベルの抵抗と自己防衛:副業時は「登録せず、値下げ交渉」で対応(取引先の8割が柔軟)。経費精算アプリ(freeeなど)で負担を最小化し、廃止まで耐える。NPO(民商)に入会し、無料相談を活用。長期的に、消費税廃止運動(れいわ新選組の支持基盤)と連動し、税制全体を変える。
これらの取り組みで、2024年の埼玉県議会可決のように、地方から国政を動かせます。副業者の声は「多様な働き方」を象徴し、政権の弱点。諦めず続け、2026年までに廃止を実現しなければ、もう日本の税制は更に毒に侵される危険(国民の命が危うくなる可能性が跳ね上がる)ことになると思いますが、あなたはどう思いますか?
#高市早苗 #インボイス #インボイス制度 #岸田文雄 #宮沢洋一

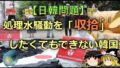

コメント