https://www.videonews.com/
マル激トーク・オン・ディマンド 第1161回(2023年7月8日)
ゲスト:三木義一氏(弁護士、青山学院大学名誉教授)
司会:神保哲生 宮台真司
これは単なる小規模事業者・フリーランス潰しなのか。それとも何か別の意図があるのか。
日本では今年10月1日からインボイス制度が導入される。これはもう確定事項だ。しかし、その影響は決して小さくない。多くの小規模事業者が廃業に追い込まれる可能性がある。また、一部では激しい反対運動も起きている。にもかかわらず、野党は一部を除き国会でも大した追求はしていないし、大手メディアもほとんど沈黙したままだ。
インボイスとはタックス・コードと呼ばれる登録番号が書かれ、消費税額が明示されている請求書のことだ。政府はこれを「適格請求書」と訳している。かつて1987年、中曽根政権下で世論や野党の反対で廃案に追い込まれた売上税というものがあったが、その時に槍玉にあげられ廃案に追い込まれる原因となった「税額票」を横文字に書き直したものがインボイスである。名前を変えれば正体がばれないとでも思ったのだろうか。今回のインボイスは、要するに正規の消費税額と消費税を納税している事業者のみに与えられる登録番号が明記された請求書のことだ。
そのインボイスを発行するためには、税務署で消費税の課税事業者として登録した上で、アルファベットのTから始まる13桁の登録者番号を取得しなければならない。このTコードを取得した瞬間に、その事業者は立派な課税事業者となり、インボイス、つまり正規の適格請求書を発行する資格を得る。もちろんその瞬間に消費税の納付義務も発生する。
日本は1989年の竹下政権下で初めて3%の消費税を導入したが、その時以来、年間売上が1,000万円以下の小規模事業者やフリーランスと呼ばれる個人事業主は消費税の納付が免除されてきた。そこには小規模事業者にとっては正しく消費税を納めるために不可欠となる正確な帳簿管理の負担が重すぎるという配慮と、自ずと逆進性の性格を持つ消費税の税負担から低所得層を解放するという2つの意味合いが込められていた。所得の多寡にかかわらず一律に消費に税金を課す消費税は、人間が生きていくためには必要最低限のものが存在することから、低所得層により重い負担を強いる性格を持っている。これが消費税の逆進性、つまり高所得者により高い税率を課す累進性の反対だ。
しかし、なぜインボイスがそこまで大きな問題で、一部で激しい反対を招いているのか。それはインボイス制度が、これまで免税扱いだった小規模事業者にとっては、課税事業者となり新たに消費税負担を強いられるか、もしくは免税事業者にとどまることで取引上不利になり、場合によっては取引から排除されるリスクを甘受するかの二者択一を迫る制度だからに他ならない。
年間売上が1,000万円以下の小規模事業者にとって、売上の10%の負担増が極めて重いものであることは言うまでもない。免税事業者が課税事業者に転じた場合、一定期間は消費税の軽減措置が設けられているが、これまで免除されていた消費税を支払わなければならなくなることに変わりはない。しかし、かといって小規模事業者が免税事業者にとどまる、つまり消費税を納めないことを選択した場合、その事業者は納税事業者にのみ発行されるTコードが取得できないためインボイスが発行できず、代わりにTコードが記載されていない旧来の請求書を出すことになる。その場合、新たな制度の下では、その請求書を受け取った取引先は、本来小規模事業者側が支払うべき消費税分まで負担しなければならなくなってしまうのだ。そうなると取引先としては、課税事業者と取引した方が得になってしまう。それが免税事業者が取引上、不利になってしまうと言われる所以だ。つまり、これまで徴収できていなかった消費税分を、免税事業者からか、もしくはその取引先からか、そのいずれかから必ず絞り取ってみせるというのが、このインボイス制度の要諦ということになる。
現在全国にある858万事業者のうち、免税事業者はおよそ500万いるとされているが、政府は今回の制度導入でそのうち約160万の事業者が課税事業者に転換することが予想され、約2,480億円の税収増が見込まれるとしている。
増収は結構なことだが、これが取るべき相手から取っているものといえるのか。そもそも消費税による税収は年間22兆円だ。今回の制度変更で増えるのはその約1%に過ぎない。その1%のために、全国500万の小規模事業者のかなりの部分が廃業に追い込まれる恐れがあるという状況が起きている。それは単純に新たな消費税の負担に堪えられないからの場合もあるし、大手事業者との取引から排除されることで、事業が成り立たなくなるという場合もあるだろう。いずれにしても日本はこの制度の導入によって、1%の消費税の増収と引き換えに、零細事業者の一斉廃業というかなりのコストを払うことになる。
インボイスを導入することの必要性について政府は、現在日本の消費税が8%と10%の複数税率になっていることを理由にあげる。2つの税率があり取引によって税率が異なるため、売上に一律に同じ税率をかけて消費税額を算出する従来の帳簿方式ではもはや正しい税額を算出できなくなっているという理屈だ。しかし、日本の消費税は基本的に一律10%で、食品とどういうわけか新聞だけに8%の軽減税率が適用されているだけだ。それと比べて欧州では消費税の逆進性を緩和するために、生活必需品などには極端に低い軽減税率が適用されている。フランスの基本消費税率は20%だが、食品や水道水、家庭用電力などは5.5%だし、同じく基本消費税が20%のイギリスでは食品や水道水、福祉補助具などは消費税は0%だ。逆進性を緩和するためにそれだけの軽減税率が実施されている国であればインボイスの必要性もわからなくはないが、税率でわずか2%しか差がなく、しかも食品と新聞というごくごく限られた商品にしか軽減税率を適用していない日本で今、零細事業者だけを狙い撃ちしたかのようなインボイス制度の導入を強行する意味がどれだけあるのか。こうして見ていくと、食品と新聞の軽減税率適用は中曽根売上税で税額票が挫折して以来、長年の念願だったインボイスを実現するために財務省が仕掛けた陰謀だったのではないかとも思いたくなってくるではないか。
日本の消費税は1989年に3%で始まり、その後3から5、5から8、8から10%へと段階的に引き上げられてきた。その一方で、その間、所得税の最高税率や法人税率は右肩下がりで引き下げられてきた。更に、金融所得に対する課税率が低いため、年間所得が1億円を超えると、所得前の負担率が右肩下がりで下がってくるという、あからさまな富裕層優遇の税制も維持されている。さらに、輸出時に消費税が企業に払い戻される輸出免税制度や繰越欠損金による課税所得控除など様々な控除や免税制度が設けられていて、大企業の税負担はいずれも極端に低いまま据え置かれている。このような富裕層と大企業を優遇した税制を放置したまま、弱い立場にある零細事業者やフリーランスから2,480億円を絞り取ろうとする政府・財務省の真意は何なのか。
もう一つの大きな問題は、大手メディアがインボイスの導入にはむしろ積極的なため、インボイスの問題点を指摘したり、せめてその内容を解説するような報道が新聞やテレビではほとんど皆無なことだ。結果的にそもそもこのような制度が導入されるという事実をほとんどの日本人が知らされていない。インボイス導入の背景に日本の軽減税率があり、新聞がその受益者になっていることから、新聞や新聞と系列化しているテレビ局もこれには反対しにくいということなのだろう。いや、もしかするとこれまであまりにも去勢されてしまった結果、もはや問題を認識する能力がなくなってしまったのかもしれない。
しかし、インボイス問題がここまでまったく報道されなかったことで、マイナ保険証の時のように、10月になって日本中が大混乱に陥らなければいいのだが。あるいはジャニーズ問題の時のように、問題が噴出してから報じ始めればいいと考えているのだろうか。
税制全体で考えた時、なぜ今回のインボイス導入が理に適っていないのか。これほど不公平な税制を大多数の国民が容認しているのはなぜか。税をめぐる議論が国民的議論に発展しない理由などについて、税制の権威として政府税調の委員などを歴任してきた元青山学院大学学長の三木義一氏と、ジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。
【プロフィール】
三木 義一 (みき よしかず)
弁護士、青山学院大学名誉教授
1950年東京都生まれ。73年中央大学法学部卒業。75年一橋大学大学院法学研究科修士課程修了。博士(法学)。静岡大学法学部教授、立命館大学法学部教授、ドイツ・ミュンスター財政裁判所客員裁判官、青山学院大学学長などを経て2019年より現職。09年、政府税制調査会専門委員。著書に『日本の税金』、『日本の納税者』、『税のタブー』など。
宮台 真司 (みやだい しんじ)
東京都立大学教授/社会学者
1959年宮城県生まれ。東京大学大学院博士課程修了。社会学博士。東京都立大学助教授、首都大学東京准教授を経て現職。専門は社会システム論。(博士論文は『権力の予期理論』。)著書に『日本の難点』、『14歳からの社会学』、『正義から享楽へ-映画は近代の幻を暴く-』、『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』、共著に『民主主義が一度もなかった国・日本』など。
神保 哲生 (じんぼう てつお)
ジャーナリスト/ビデオニュース・ドットコム代表 ・編集主幹
1961年東京都生まれ。87年コロンビア大学ジャーナリズム大学院修士課程修了。クリスチャン・サイエンス・モニター、AP通信など米国報道機関の記者を経て99年ニュース専門インターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』を開局し代表に就任。著書に『地雷リポート』、『ツバル 地球温暖化に沈む国』、『PC遠隔操作事件』、訳書に『食の終焉』、『DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機』など。
【ビデオニュース・ドットコムについて】
ビデオニュース・ドットコムは真に公共的な報道のためには広告に依存しない経営基盤が不可欠との考えから、会員の皆様よりいただく視聴料(月額500円+消費税)によって運営されているニュース専門インターネット放送局です。(www.videonews.com)
(本記事はインターネット放送局『ビデオニュース・ドットコム』の番組紹介です。詳しくは当該番組をご覧ください。)
#マル激 #インボイス #三木義一 氏 #消費税 #神保哲生 #宮台真司
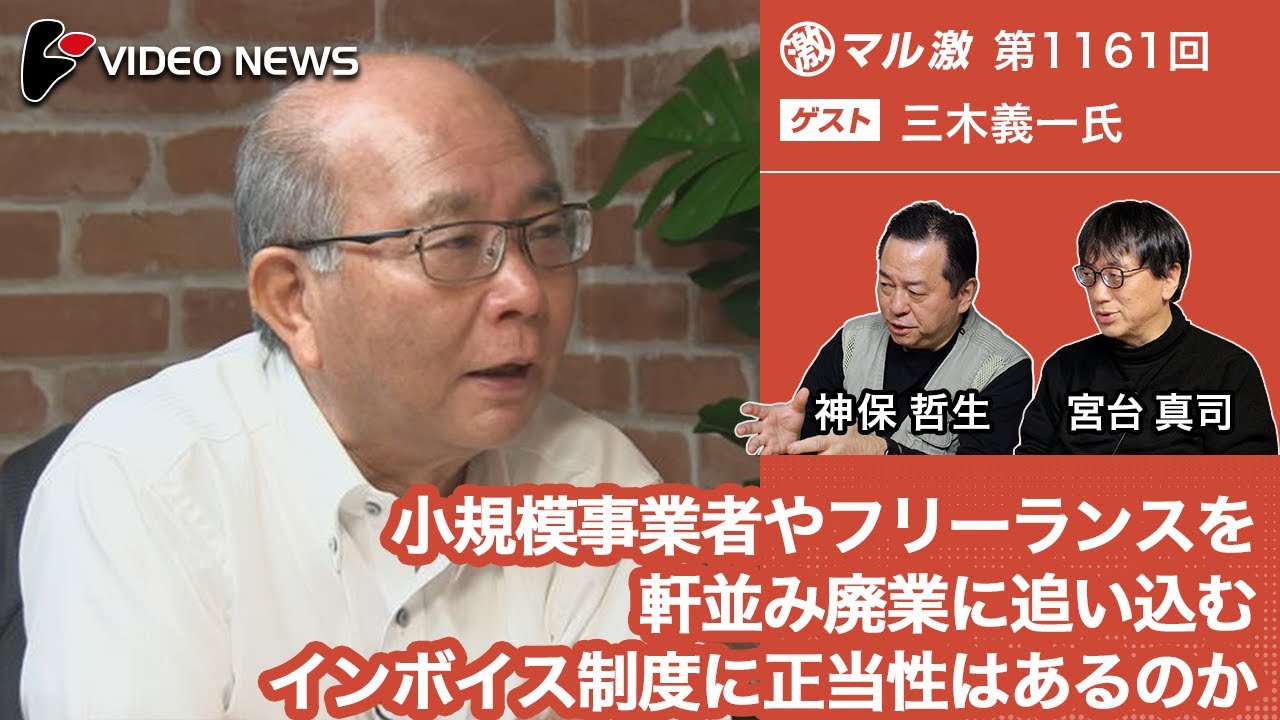


コメント