武見厚労相が、少子化対策は今がラストチャンスである、と語った。本当か?とびっくりするような話だ。そもそも少子化対策にラストチャンスがあったかどうかはわからないが、あったとしても何十年も前の話で、今は少子化は予想ではなく、完全なる事実となって、その滑り台を直行している最中だ。対策がもし本当にあるのだったら、どうしてあなたの父親の世代がそれをやらなかったのか、と思う。
そうだとしても、少子化時代の一体何が悪いのだろうか。経済に悪影響がある?今や、日本の大手企業は、大体海外で主要なビジネスを展開しており、日本の労働人口が減ってもそんなに困らない。それに、三大都市圏の人口統計を見ると、それは決して減っていないので、採用に苦しむこともそんなに考えられない。
もちろん三大都市圏じゃない地方では、急激な人口減に見舞われる。しかし、産業構造の変化にうまく乗りさえすれば、その地方が上昇気流をつかむチャンスはいくらでもある。
地方は農耕で生計を立てなければならない、というようなルールはどこにもない。時代は、農耕社会から工業化社会を経て、今まさに情報化社会がはじまったところだ。情報化社会のフレームワークは、これから構築されるところである。
これまでの情報化は、それを必要とするそれぞれの企業が独自に情報システム部門を持ち、バラバラに運用するような段階だった。しかし、それでは技術の進歩や経費の増加に企業経営が追い付かない。そこで、情報処理は、データセンターに丸投げしてしまう、というのが、今はじまっている流れだ。
ソフトバンクがシャープの堺工場の結構な割合の設備を利用して、大型のデータセンターをつくる、との発表があった。データセンターはNTTやソフトバンクなどが開拓しつつある新産業だ。彼らは顧客に近い首都圏や近畿圏にデータセンターを開発しただけではなく、ソフトバンクは北海道との提携を発表しており、まず手始めに苫小牧に超大型のデータセンターを設立すると言っている。
情報化社会は、巨大なデータセンターというインフラを必要とする。そして、情報の安全のために、各データセンターはお互いにバックアップを取りつつ遠隔地に設置されることが望ましい。過疎であることは、土地や潜在的な電力供給の可能性に富んでいる、ということであるから、データセンターの設置には非常に有利である。都市部の、土地の価格が高く、電力の余剰に疑問のある場所に巨大なデータセンターを設置することは考えられず、そこには顧客の近くであることが必須なエッジ型の小規模なデータセンターしか置くことができないだろう。
地方にとってのビジネスチャンスは、情報化社会の進展とともにどんどん広がる。そして、そうしたイノベーションの妨げとなる地方の有力者なる存在は、すでに高齢であり、どんどん他界する。そして、おそらくその子女たちは都会の大学に行き、田舎になど帰って来ない。地方が変わるための材料は整っている。あとは地元の方々がやるかやらないか、ということだけだろう。
#少子化 #データセンター #アップグレードする日本
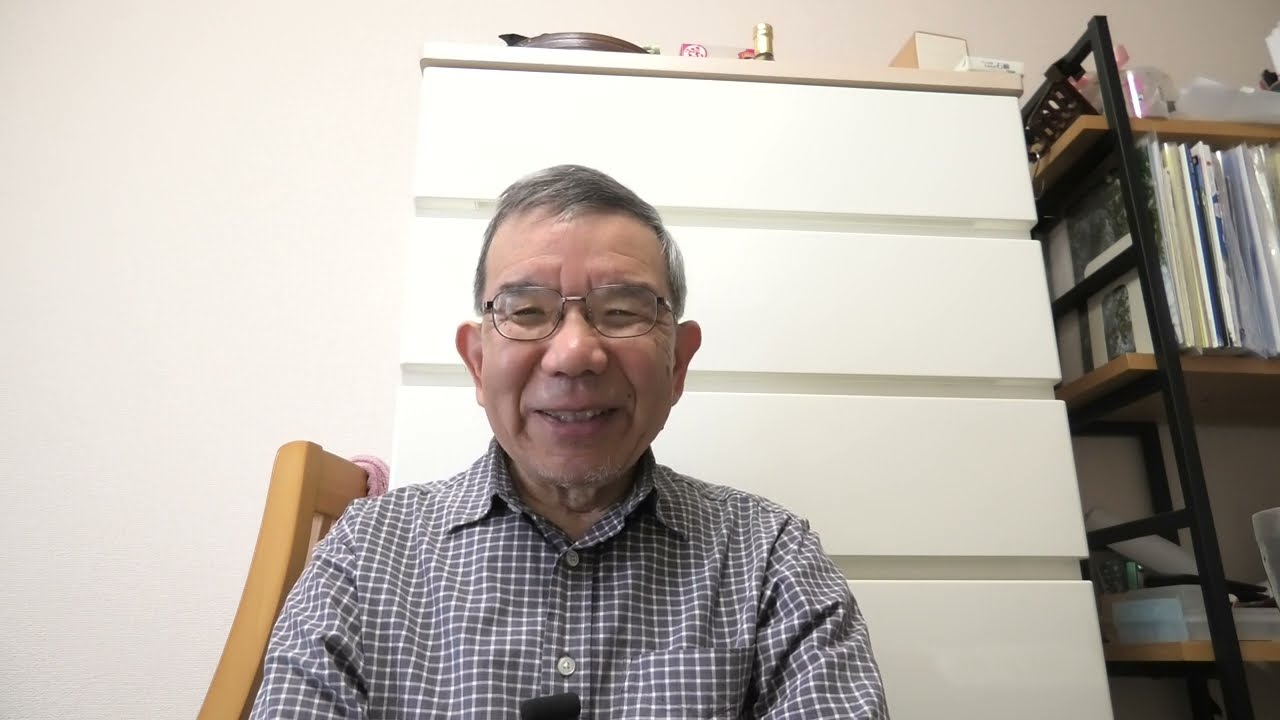


コメント